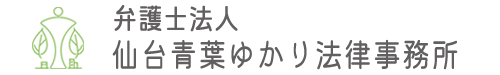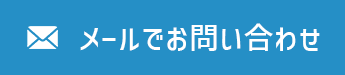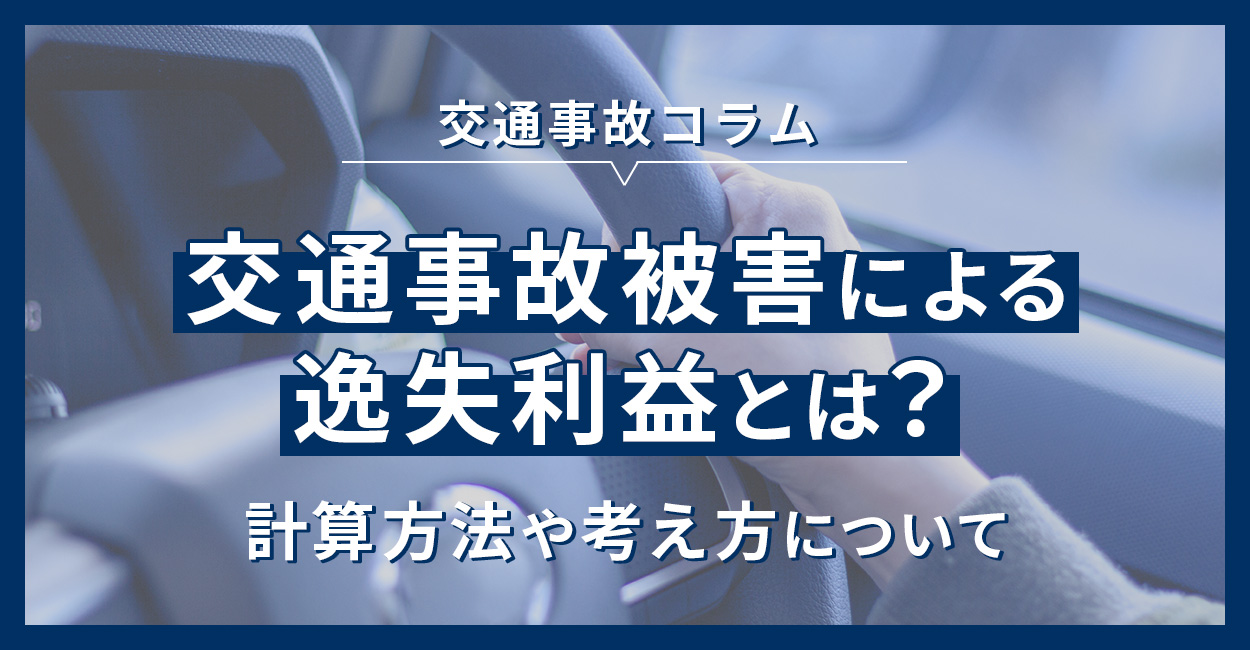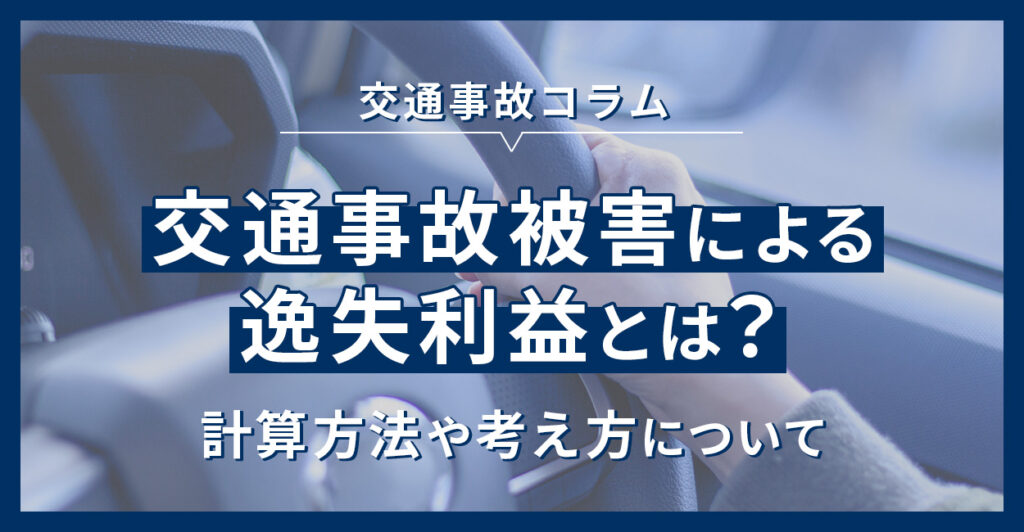
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償をします。損害賠償と一言でいっても様々な内訳があるのですが、その中の1つが逸失利益です。逸失利益とはどのようなものなのでしょうか。またどのように計算するのでしょうか。
本記事では交通事故の被害者が請求する逸失利益とその計算方法について解説します。
逸失利益とは
逸失利益とは、本来得られたにもかかわらず、不法行為などが原因で得られなくなった利益のことをいいます。
逸失利益の基本的な考え方
逸失利益の基本的な考え方を確認しましょう。
働いている人は毎月給与をもらいますが、交通事故で働けなくなってしまうと、その給与は得られなくなってしまいます。その得られなくなってしまった給与分は交通事故における立派な損害であり、加害者に請求できるものです。これが逸失利益の基本的な考え方であり、交通事故において損害賠償請求する内訳の1つとなります。
逸失利益の種類
交通事故において逸失利益として次の2つの種類があります。
- 死亡逸失利益
- 後遺障害逸失利益
それぞれ具体的な内容を見てみましょう。
死亡逸失利益
交通事故の被害者が死亡した場合の逸失利益が死亡逸失利益です。
交通事故の被害者が亡くなってしまうと、当然ですがもう働くことができなくなります。そのため、得られたのに得られなかった給与などを得ることができません。そのため逸失利益を請求できます。これが死亡逸失利益です。
後遺障害逸失利益
交通事故の被害者が後遺障害等級認定された場合に請求できるのが後遺障害逸失利益です。
重篤な交通事故の被害にあった場合、後遺症が残ることがあります。後遺症によって日常生活に影響が出ると、当然仕事にも影響します。寝たきりになると仕事ができなくなるのはもちろん、後遺症の内容次第で、軽い内容の仕事しかできなくなる、短時間しか労働できなくなる、などの影響を受けるでしょう。
後遺症が残った場合、その重篤度に応じて設定されている後遺障害等級認定がされます。そこで後遺障害として認定された等級に応じて請求できる逸失利益が、後遺障害逸失利益です。
交通事故における逸失利益の計算方法
では、交通事故における逸失利益の計算方法を確認しましょう。
交通事故における逸失利益の計算は次のように行います。
| 種類 | 計算方法 |
| 死亡逸失利益 | 1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数 |
| 後遺障害逸失利益 | 1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
得られなかった給与なので、年収✕定年までの年数で計算すればシンプルです。しかし、損害賠償請求は一括で支払うのが原則です。将来もらえるはずであった給与を前倒しでもらう場合そのお金を銀行に預ければ利息を得ることができ、得であると法律上では評価できます。
損害賠償請求を認めた趣旨は損害の公平な分担であり、もらえる時期が前倒しになることで得をするまでは認めていません。これら損害の公平な分担という考え方にそった結果が上記の計算式であり、非常に複雑になっています。
基礎収入
基礎収入とは、その人が得ていた収入のことをいいます。
基本的には事故を起こした前年度の年収で計算します。なお現実に就労しているわけではない専業主婦・子どもについても逸失利益の請求は可能で、この場合賃金センサスという統計資料に基づいて計算します。
生活費控除率
死亡逸失利益の計算において問題になるもので、被害者が使ったであろう生活費分を考慮するためのものです。被害者が死亡した場合の逸失利益を考える場合、生きていたならば生活費として使った分もあるはずです。その分については控除するのが損害の公平な分担という考え方からフェアなので計算式に入れられているのが生活費控除率です。
生活費控除率は、次の割合を基本に個別具体的な事情を斟酌して決めます。
| 属性 | 割合 |
| 男性 | 50% |
| 女性 | 40% |
| 被害者が一家の支柱(被扶養者が1人) | 40% |
| 被害者が一家の支柱(被扶養者が2人以上) | 30% |
就労可能年数
交通事故で亡くなっていなければ働けたであろう年数のことで、原則として67歳で計算します。
ライプニッツ係数
逸失利益から中間利息を差引くための係数のことを、ライプニッツ係数といいます。
中間利息とは、資産運用などで生じる利息のことをいいます。ライプニッツ係数は国土交通省のホームページに掲載されています。
参考:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省(PDF)
労働能力喪失率
後遺障害逸失利益の計算における、後遺障害によってどの程度労働能力を喪失したのかの割合が、労働能力喪失率です。自賠責保険の請求で認定された後遺障害等級に応じて次のように計算します。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
| 第1級 | 100% |
| 第2級 | 100% |
| 第3級 | 100% |
| 第4級 | 92% |
| 第5級 | 79% |
| 第6級 | 67% |
| 第7級 | 56% |
| 第8級 | 45% |
| 第9級 | 35% |
| 第10級 | 27% |
| 第11級 | 20% |
| 第12級 | 14% |
| 第13級 | 9% |
| 第14級 | 5% |
まとめ
本記事では、交通事故の被害者が加害者に請求する逸失利益について解説しました。
将来得られるはずだった利益のことをいい、損害賠償の内訳として請求できるものなのですが、その計算式は非常に複雑です。後遺症が発生するような交通事故では、後遺障害等級認定を有利にする、後遺障害慰謝料を正しい基準で計算するなど、請求を有利にするためのポイントがいくつもあります。
弁護士に相談・依頼して、適切な損害賠償をすることをおすすめします。