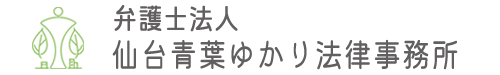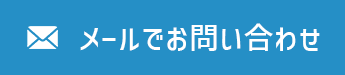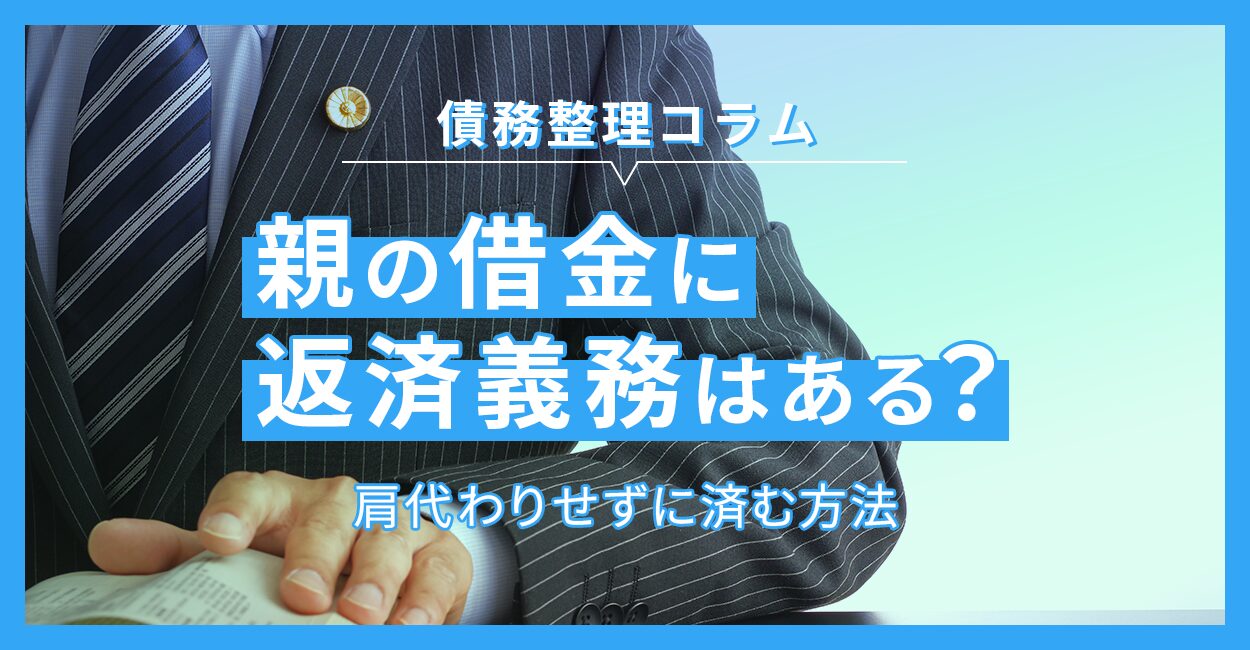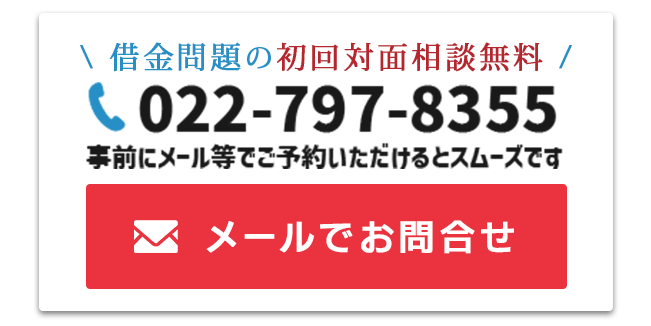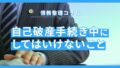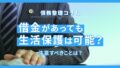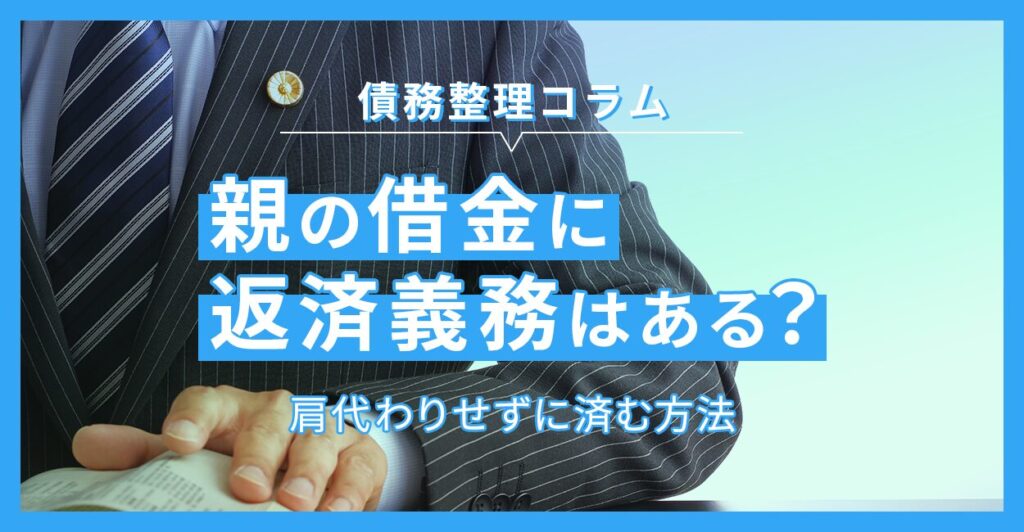
親が多額の借金を抱えていると知ったとき、「自分が代わりに返さなければならないのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。しかし、法律上、親子であっても借金の支払い義務は負いません。連帯保証人になっていたり、相続の方法を誤ると、思わぬ返済義務を負う可能性もあります。
本記事では、親の借金に対して子が返済義務を負うケースとそうでないケースと、肩代わりせずに済むための具体的な方法についても解説します。
親の借金を子が支払う義務はあるのか
親の借金を子が支払う義務はありませんが、特定の場合には支払義務が生じます。その法的な理由について確認しましょう。
親の借金は支払う義務はない
原則として、親の借金を子が返済する法的義務はありません。たとえ親子であっても契約当事者でなければ支払義務は生じず、親が借りたお金を子が代わりに返済する必要はありません。道義的に支払いたいと思う場合は別ですが、債権者が法的に子どもに請求できる法的根拠はありません。
ただし、悪質な債権者は言葉巧みに交渉をして、子が債務を引き受ける・保証人となる書面に署名をさせて、子に債務の履行を求めることがあります。このようなケースでは争うことが難しくなるので、安易に親が債務の支払いができなくなった場合に債権者が差し出す書面に署名をしないようにしましょう。
連帯保証人となっている場合は自分が負っている保証債務として支払う義務
親の借金に対して子どもが連帯保証人になっている場合、その借金は「自分の債務」として返済義務が生じます。
連帯保証人は主債務者と同等の立場で責任を負うため、親が返済できないときには、貸金業者などから直接請求を受けることになります。この義務は非常に重く、一括請求や強制執行の対象になる可能性もあります。
保証契約は一度締結すると返済しないと解消ができないので、署名前に内容をしっかり確認しましょう。
相続をした場合には自分の債務として支払う義務
親が亡くなった後に相続をすると、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになります。相続人が遺産を単純に承認した場合、借金も法的に承継され、自分の債務として返済しなければなりません。
現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンが多い場合もあるため、相続は慎重に判断する必要があります。
親の借金を肩代わりせずに済む方法
親の借金であっても、条件次第では子が返済を迫られる場面もあります。しかし、適切な対応をすれば法的責任を回避することが可能です。ここでは、親の借金を肩代わりせずに済む具体的な方法について解説します。
親に存命中に債務整理してもらう
親が存命中であれば、自分が代わりに返済するのではなく、親自身に債務整理をしてもらうことが現実的な解決策です。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産などの手続きがあり、収入や財産の状況に応じて選択可能です。これにより借金が減額・免除されることもあり、子どもが連帯保証人になっていない限り、返済義務を回避できます。
親が自分の借金問題に向き合うことが、家族全体の負担軽減につながります。
保証債務の無効を主張する
もし親の借金に対して「自分が連帯保証人になっている」と言われた場合でも、本人が契約をしていない場合、保証債務の無効を主張できる可能性があります。保証人は債権者や債務者が勝手に指定できず、保証人となる人がきちんと保証契約する必要があります。そして、保証契約は書面によって行う必要があり(民法第446条第2項)、保証人自らが書面を作成する必要があります。
親が勝手に保証人として契約書に名前を書いた場合には保証人本人が書面で保証したわけではないので、無効を主張できる可能性があります。保証契約をした覚えがないのに保証人として請求されている場合には、契約書の提出を求め、筆跡が違う・押印がないなどの主張によって反論することになります。
相続放棄・限定承認をする
親が亡くなったあとに借金が発覚した場合は、「相続放棄」または「限定承認」によって借金の肩代わりを回避できます。
相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、親の借金も一切引き継ぎません。一方、限定承認は「相続財産の範囲内」で借金を返す手続きで、遺産の中にプラスの財産もある場合に有効です。どちらも原則として相続発生を知ってから3か月以内に手続きする必要があるため、早めの対応が欠かせません。
まとめ
親の借金があるからといって、子には法的に支払い義務はありません。しかし、連帯保証人になった・相続したような場合は自分の債務として支払義務を負います。
相続については相続放棄や限定承認を選ぶことで親の借金を肩代わりすることを回避できます。また、保証契約を勝手に結ばれた場合には無効を主張できます。相続放棄をするためには3ヶ月の期間制限があります。
また、保証債務の無効を主張するためには適切な主張と証拠の収集が欠かせません。そのため早めに弁護士に相談するようにしてください。