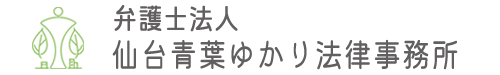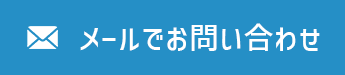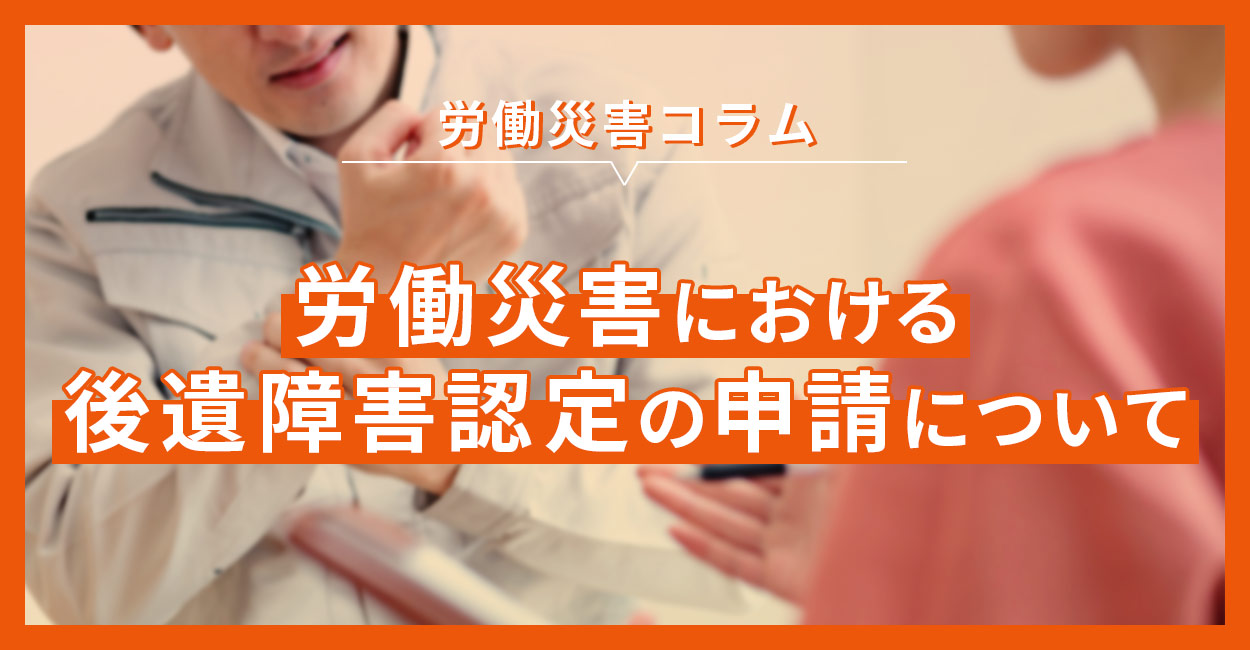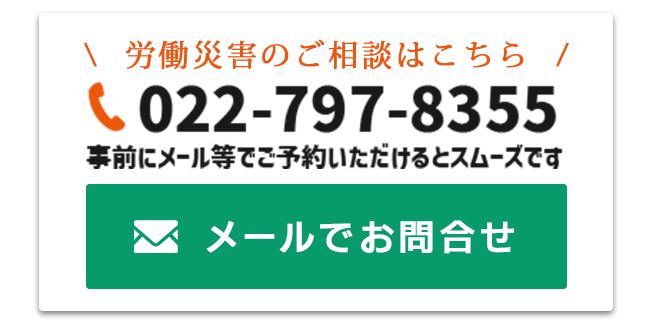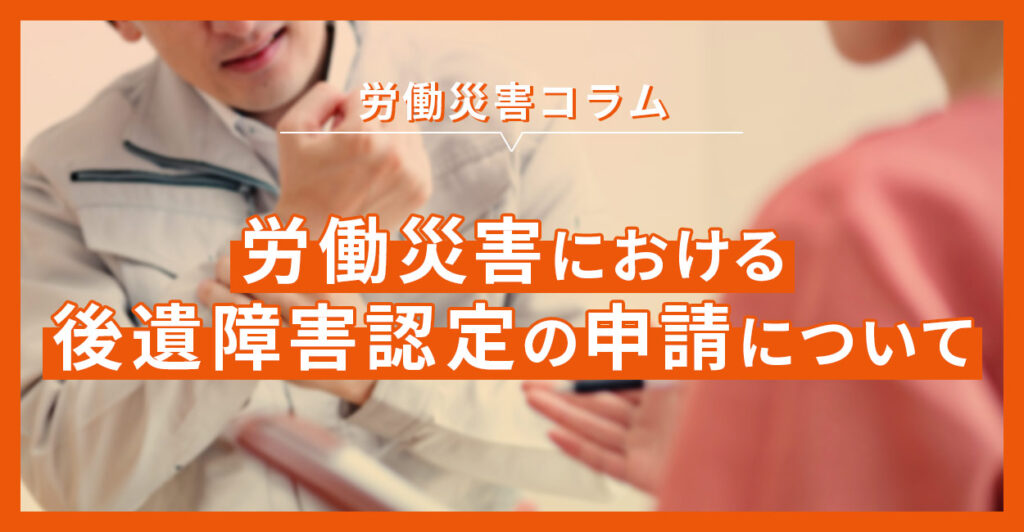
仕事で怪我や病気になった場合や、通勤中に怪我をした場合、労災保険給付を受けることができます。
労災保険給付にはいくつかの種類がありますが、怪我や病気が重篤な場合、後遺症が残った場合に問題になるのが障害(補償)等給付などで、その給付を受けるために欠かせないのが後遺障害等級認定です。
本記事では後遺障害等級認定の申請について解説します。
労働災害における後遺障害等級認定とは
労働災害(労災)における後遺障害等級認定とは、後遺症が残った場合に、障害(補償)等給付の金額を決定するための等級認定のことです。
労災に被災した場合、怪我や病気が重いと後遺症が残る場合があります。後遺症が残ってしまった場合、障害(補償)等給付などを受けられることがありますが、その内容は後遺症の重篤度に応じた後遺障害等級によって決定されます。
後遺障害等級認定は、この後遺障害等級を認定してもらうための手続きであり、労災に被災して後遺症が残った場合に非常に重要なものです。
後遺障害等級に応じた給付内容
では労災に被災して残った後遺症が後遺障害等級認定された場合の給付内容を確認しましょう。
| 障害等級 | 障害(補償)等給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 | ||||
| 第1級 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | 一時金 | 342万円 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | – | – |
| 第2級 | 年金 | 給付基礎日額の277日分 | 一時金 | 320万円 | 年金 | 給付基礎日額の277日分 | – | – |
| 第3級 | 年金 | 給付基礎日額の245日分 | 一時金 | 300万円 | 年金 | 給付基礎日額の245日分 | – | – |
| 第4級 | 年金 | 給付基礎日額の213日分 | 一時金 | 264万円 | 年金 | 給付基礎日額の213日分 | – | – |
| 第5級 | 年金 | 給付基礎日額の184日分 | 一時金 | 225万円 | 年金 | 給付基礎日額の184日分 | – | – |
| 第6級 | 年金 | 給付基礎日額の156日分 | 一時金 | 192万円 | 年金 | 給付基礎日額の156日分 | – | – |
| 第7級 | 年金 | 給付基礎日額の131日分 | 一時金 | 159万円 | 年金 | 給付基礎日額の131日分 | – | – |
| 第8級 | 一時金 | 給付基礎日額の503日分 | 一時金 | 65万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の503日分 |
| 第9級 | 一時金 | 給付基礎日額の391日分 | 一時金 | 50万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の391日分 |
| 第10級 | 一時金 | 給付基礎日額の302日分 | 一時金 | 39万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の302日分 |
| 第11級 | 一時金 | 給付基礎日額の223日分 | 一時金 | 29万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の223日分 |
| 第12級 | 一時金 | 給付基礎日額の156日分 | 一時金 | 20万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の156日分 |
| 第13級 | 一時金 | 給付基礎日額の101日分 | 一時金 | 14万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の101日分 |
| 第14級 | 一時金 | 給付基礎日額の56日分 | 一時金 | 8万円 | – | – | 一時金 | 給付基礎日額の56日分 |
給付基礎日額とは、労災保険給付を計算するためのもので、労災が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額をいいます。
例えば、背中や首を強く打ち、むちうちの症状が後遺症として残った場合、第12級あるいは第14級に認定されるか、全く認定されない、という可能性があります。給付基礎日額が1万円だとすると、第12級に認定されれば上記で合計332万円が、第14級に認定されれば120万円が支払われ、認定されなければ障害(補償)等給付は全く支払われません。
そのため、後遺障害等級認定は後遺症が残ってしまった場合には重要です。
後遺障害等級認定の申請の流れ
後遺障害等級認定の申請は次のような流れでおこなわれます。
症状固定
後遺障害等級認定の申請は、症状固定の後におこなわれます。症状固定とは、後遺症が治療をしてもこれ以上良くならない状態です。
症状固定によって後遺症をどのように認定すべきかが確定するので、その後に後遺障害等級認定の申請を行います。
請求書(申請書)を作成・添付書類を収集して労働基準監督署に申請をする
申請書を作成し、添付書類を収集して労働基準監督署に申請します。申請書は、厚生労働省ホームページの「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html)でダウンロードができます。
添付書類として必要なのは次の2種類です。
- 労災用の後遺障害診断書
- 自己申立書(障害の状態に関する申立書)
後遺障害等級の審査・認定
労働基準監督署で審査が行われ、その結果に基づいて認定がされます。
認定内容に不服がある場合には審査請求・再審査請求・裁判などの方法で不服申立てができます。
労働災害で後遺症が残った場合には会社に損害賠償請求ができる
後遺症が残る怪我を負った場合、障害(補償)等給付以外にも、療養(補償)等給付・休業(補償)等給付・介護(補償)等給付などの補償を受けられます。ただし、休業(補償)等給付については補償が全額ではなく、慰謝料も労災保険給付としては支払われません。
これらの損害については、会社に対して使用者責任(民法第715条)や安全配慮義務(労働契約法第5条)をもとに損害賠償請求ができます。
まとめ
本記事では、労働災害における後遺障害等級認定について解説しました。後遺症が残ってしまった場合、その重篤度に応じて後遺障害等級認定が行われ、認定された等級に基づいて年金・一時金の形で支払いがされます。
認定される等級によっては受けられる補償が少なくなってしまい、その後の生活に影響します。労災で後遺症が残ってしまった場合には、症状固定となる前の治療の段階から、弁護士に相談することをおすすめします。