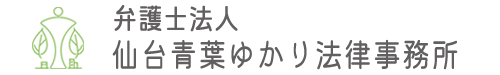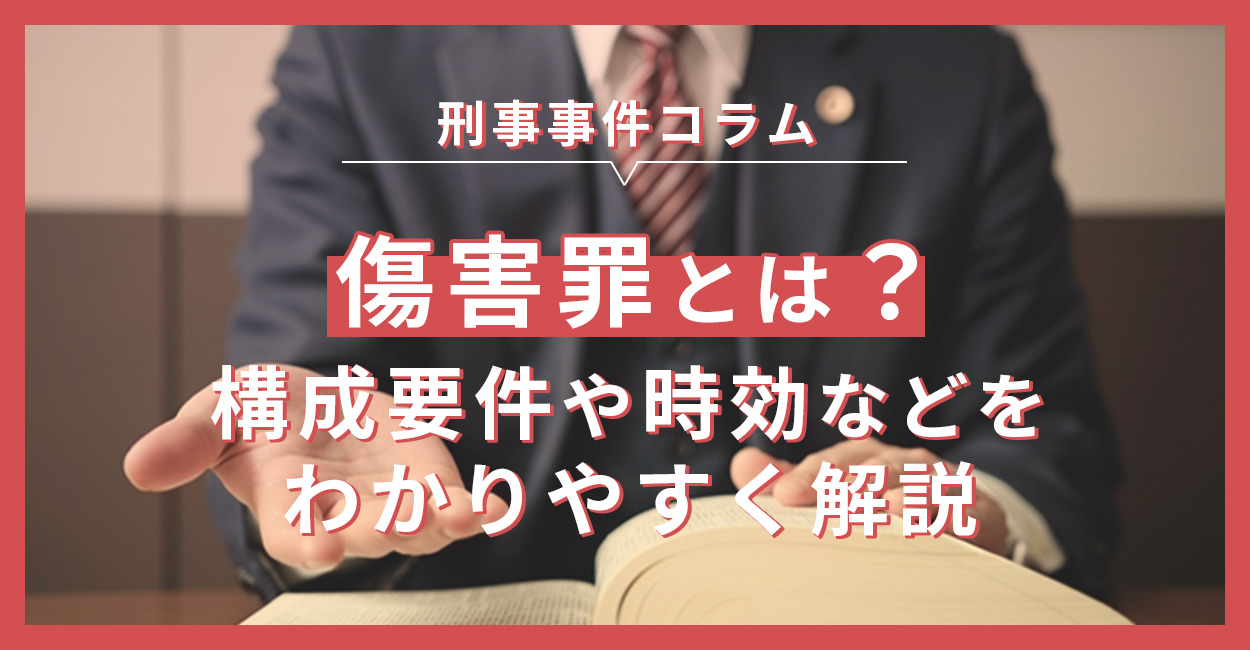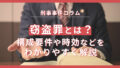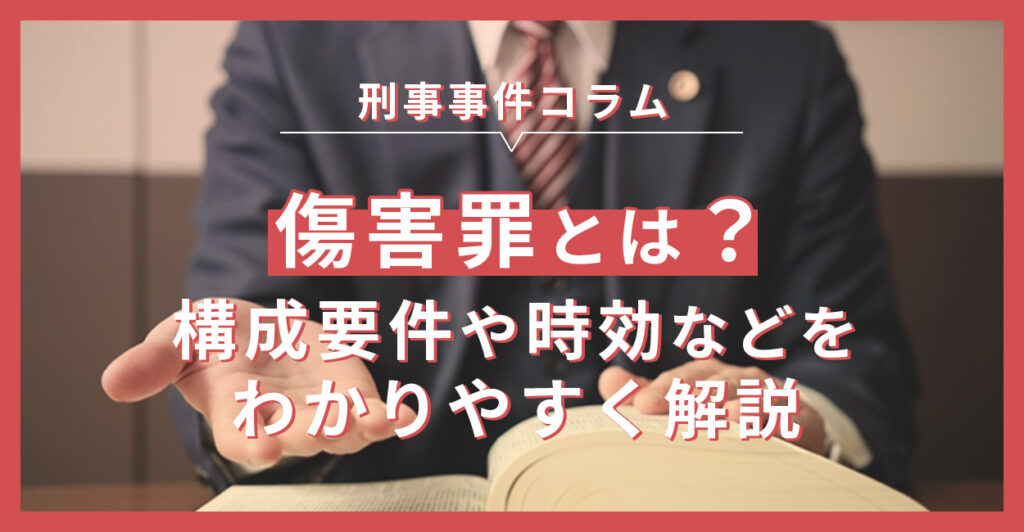
傷害罪は、喧嘩やいじめなど日常生活のトラブルからも起こりやすい犯罪の1つです。しかし、法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、決して軽い犯罪とはいえません。
今回は、傷害罪を理解するために、傷害罪の構成要件や傷害罪と暴行罪の違い、時効、傷害罪で逮捕されるとどうなるのかを解説します。
傷害罪とは?
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する犯罪です(刑法204条)。
| (傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 引用:刑法|e-Gov法令検索 |
「傷害」の典型例はケガをさせることですが、「傷害」になるのはそれだけではありません。判例では、性行為で性病をうつす行為や精神的なダメージを与えてPTSDを発症させる行為も「傷害」にあたると認定しています。
ここからは、傷害罪の構成要件、傷害罪と暴行罪の違い、傷害罪の時効について詳しく解説します。
傷害罪の構成要件
傷害罪の構成要件である「傷害」の定義については、学説の見解が分かれています。
そのうち最も有力なのは、「傷害」を他人の身体の生理的機能を害する行為と定義する見解です。判例もこの見解を採用しています。この見解によると、相手にケガをさせなくても、病気を発症させる行為は身体の生理的機能を害する行為として「傷害」にあたります。
その他に有力なのは、「傷害」を身体の完全性を侵害する行為と定義する見解です。この見解では、病気を発症させる行為はもちろんのこと、髪の毛を切る行為も「傷害」にあたります。判例では、女性の髪の毛を切った行為について暴行罪が成立するとしており、この見解を採用していないことは明らかです。
近年は、両者を合わせた折衷説も有力となっていますが、基本的には判例に従って、「傷害」とは人の身体の生理的機能を害する行為と理解しておくのが良いでしょう。
傷害罪と暴行罪の違い
暴行罪は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する犯罪です(刑法208条)。
| (暴行)第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 引用:刑法|e-Gov法令検索 |
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行為全般を意味します。判例では、人の身体に塩を振りかけた行為に暴行罪が成立すると認定したものがあります。
傷害罪と暴行罪は、どちらも人の身体に対して不法な有形力を行使する犯罪です。その結果、相手の身体の生理的機能を害した場合には傷害罪が成立し、そうでない場合には暴行罪が成立します。傷害罪と暴行罪の法定刑には大きな差がありますが、傷害罪が暴行罪と比べて重く処罰されるのは、相手に傷害を負わせたことが強い非難に値するからです。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯としての性質も持っています。結果的加重犯とは、軽い犯罪を犯す意思しかなかったにも関わらず、結果的に重い犯罪を犯してしまった場合でも、重い犯罪で処罰されることを意味します。傷害罪と暴行罪の関係では、犯人に被害者をケガさせる意図がなくても(重い傷害罪の故意がなくても)、暴行によってケガをしてしまったときには、重い傷害罪が成立します。
傷害罪の時効
傷害罪の時効は10年です(刑事訴訟法250条2項3号)。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。公訴時効について規定する刑事訴訟法250条では、「長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年」(同条2項3号)と規定されているため、傷害罪の公訴時効は10年です。
なお、傷害行為について民事上の損害賠償を請求する場合の時効は、被害者が犯人を知ってから3年もしくは傷害行為のときから20年となります(民法724条)。そのため、公訴時効が成立しても、民事上の損害賠償請求の時効は成立していないというケースもあり得ます。
傷害罪で逮捕されるとどうなるか?
ひと言に傷害罪といっても、傷害の程度によって逮捕された後の流れは大きく変わります。
たとえば、酔っぱらい同士の喧嘩で相手のケガの程度も軽い場合には、逮捕されたとしても勾留前に釈放される可能性も十分にあります。
起訴・不起訴を分ける判断要素としては、次のようなものが挙げられるでしょう。
- 傷害の程度
- 暴行に至った経緯、暴行の内容
- 前科・前歴の有無
- 反省の有無
- 示談成立の有無
傷害罪については示談成立の有無が起訴・不起訴を分ける決定的な要素となるケースも少なくありません。犯人に前科がなく、傷害の程度も後遺症が残るほど大きなものでない場合には、示談さえ成立すれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
犯人に同種前科がある場合、示談が成立しても起訴や実刑判決が下される可能性があります。傷害の結果が重大なものであれば、初犯でも実刑判決を覚悟する必要があるでしょう。