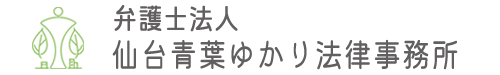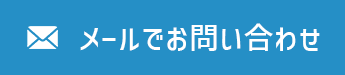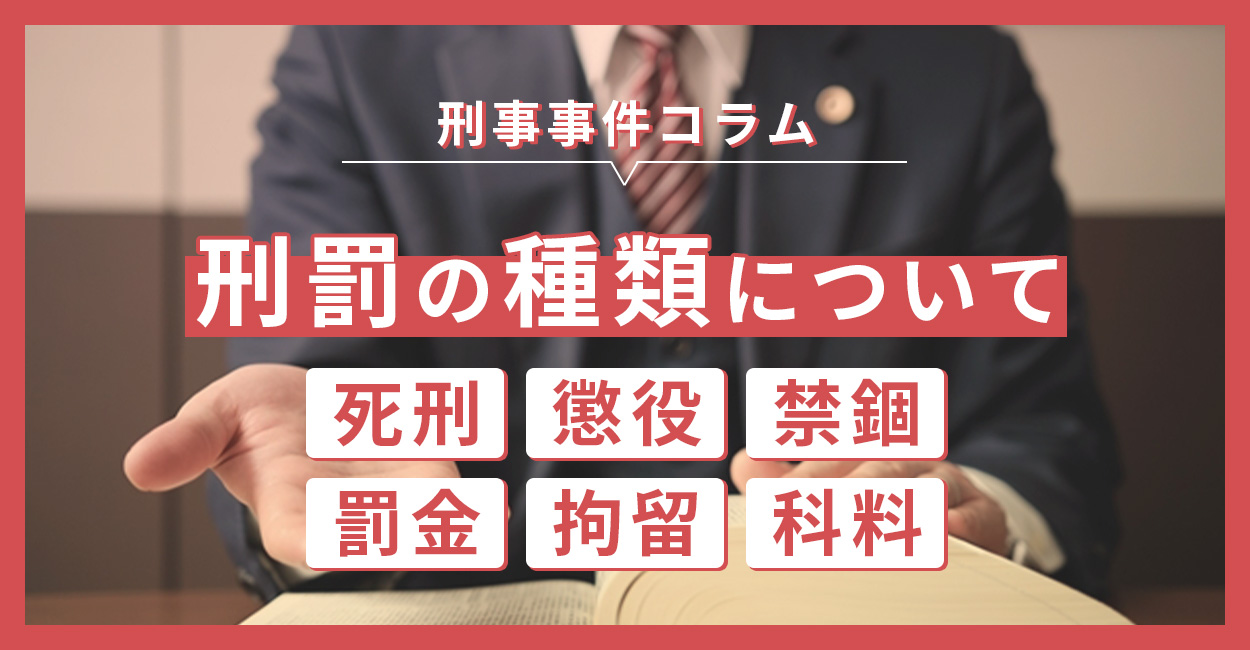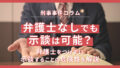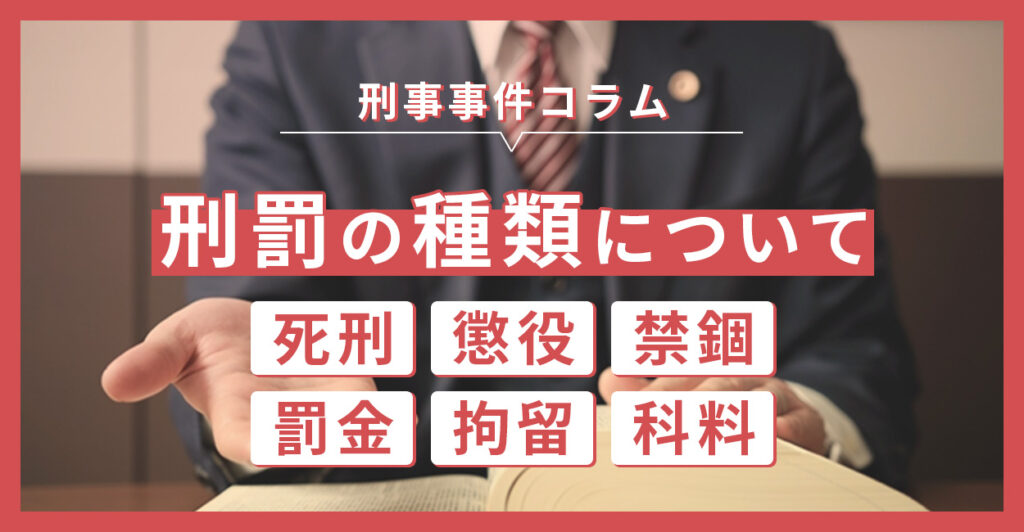
犯罪を犯してしまった場合、裁判で刑罰を受けることになります。では刑罰にはどのような種類があるのでしょうか。本記事では刑罰の種類について解説します。
刑罰の種類
刑罰には次のような種類があります。
| 種類 | 法律 | 内容 |
| 死刑 | 刑法第11条 | 生命を奪う刑 |
| 懲役 | 刑法第12条(令和5年7月13日施行) | 刑務所内に拘置し所定の作業義務を科す刑罰 |
| 禁錮 | 刑法第13条(令和5年7月13日施行) | 刑務所内に拘置し所定の作業義務を科さない刑罰 |
| 拘禁刑 | 刑法第12条(令和7年6月1日施行) | 刑務所内に拘置する刑罰 |
| 罰金 | 刑法第15条 | 強制的に金銭を支払わせる刑罰 |
| 拘留 | 刑法第16条 | 刑務所内に拘置し所定の作業義務を科さない刑罰のうち短期のもの |
| 科料 | 刑法第17条 | 強制的に金銭を支払わせる刑罰のうち少額のもの |
| 没収刑 | 刑法第19条 | 犯罪に関係のある物の所有権を奪うもの |
死刑
刑の種類に、行為者の生命を奪う死刑があります。
刑法第11条に規定されており、刑務所において、絞首して執行することが法定されています。死刑を宣告するには、下記の、いわゆる永山基準によって判断します。
- 犯罪の性質
- 犯行の動機
- 犯行態様
- 結果の重大性
- 遺族の被害感情
- 社会的影響
- 犯人の年齢
- 前科
- 犯行後の情状
なお、犯行態様としては特に殺害方法の執拗性・残虐性が重視され、結果の重大性としては特に殺害された被害者の数が重視されます。
懲役
刑務所内に拘置し所定の作業義務を科す刑罰が懲役です。
刑務所内に拘置される点で禁錮と同様ですが、作業義務がある点で禁錮と異なります。なお、懲役は令和7年6月1日に施行される刑法からは禁錮と統合された拘禁刑となります。なお、同じように刑務所内に拘置し所定の作業義務を科す刑罰に拘留がありますが、拘留は30日未満である一方、懲役は有期懲役の場合でも1か月以上20年以下が原則です。
懲役には期間が決まっている有期懲役と、期間が決まっていない無期懲役があります。有期懲役は原則として1年以上20年以下ですが、過重する場合には30年まで延長され、減軽する場合には1ヶ月未満の懲役とすることができます。3年未満の懲役の場合には情状によって刑の全部または一部の執行の猶予をすることができます(いわゆる執行猶予)。
禁錮
刑務所内に拘置し所定の作業義務を科さない刑罰が禁錮です。
作業義務を科す懲役と異なり、禁錮の場合は作業義務は科されません。上述したように禁錮は令和7年6月1日より、拘禁に統合されます。禁錮も懲役と同様に執行猶予をすることができます。
拘禁刑
刑務所内に拘置する刑罰のことを拘禁刑といいます。
刑務所内に拘置する刑罰です。従来の懲役と異なり、リハビリや更生指導が行えるよう改正されたのが拘禁刑です。
罰金
強制的に金銭を支払わせる刑罰が罰金です。
同じように強制的に金銭を支払わせる刑罰に科料がありますが、罰金は1万円以上のものをいい、1,000円以上1万円以下のものが科料です。法人は懲役・禁錮・拘禁刑に処せられませんが、罰金を科すことができます。同じように罰として行為者に支払わせるものに過料がありますが、こちらは刑事罰ではなく一定の行為を促すなどで設けられている行政罰です。罰金の場合も50万円以下であれば執行猶予とすることができます。
労役場留置
なお、罰金を納めることができない場合には労役場留置がおこなわれます(刑法第18条)。
労役場に留置して、労役から得た収益で罰金を払うもので、刑務所・拘置所の中で労働に従事します。
拘留
刑務所内に拘置し所定の作業義務を科さない刑罰のうち短期のものを拘留といいます。
懲役とは異なり、拘留には作業義務がありませんが、刑務所内で拘束される点は共通しており、その期間が1日以上30日未満の短期のものが拘留です。
科料
強制的に金銭を支払わせる刑罰のうち少額のものが科料です。
罰金との違いは罰金は1万円以上であるのに対して、科料は1,000円以上1万円以下の少額のものなのは上述した通りです。行政罰である過料と読み方が一緒なので、両者を区別するために、実務上「とがりょう」と呼ぶことがあります(なお、過料は「あやまちりょう」)。
没収
犯罪に関係のある物の所有権を奪うものが没収です。
たとえば殺人事件において使用された凶器や、盗撮に利用したカメラなど、犯罪に関係のある物の所有権を奪う刑罰が没収で、その他の刑罰に付加されるものである点で、付加刑と呼ばれます。次の場合に没収が認められます。
- 犯罪行為を組成した物
- 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
- 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
- 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は犯罪行為に付加して行われるものであり、没収のみが行われることはありません。
まとめ
本記事では、刑罰の種類について解説しました。刑罰は、自由を奪う期間や没収される財産の額によって呼び方が異なります。特に懲役や禁錮(改正後は拘禁刑)の場合、執行猶予が認められることもあります。そのため、重大な犯罪で刑に問われた場合でも、身柄の解放を目指して弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。