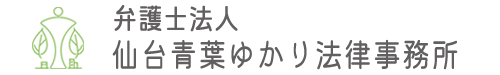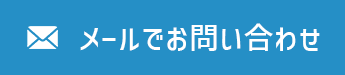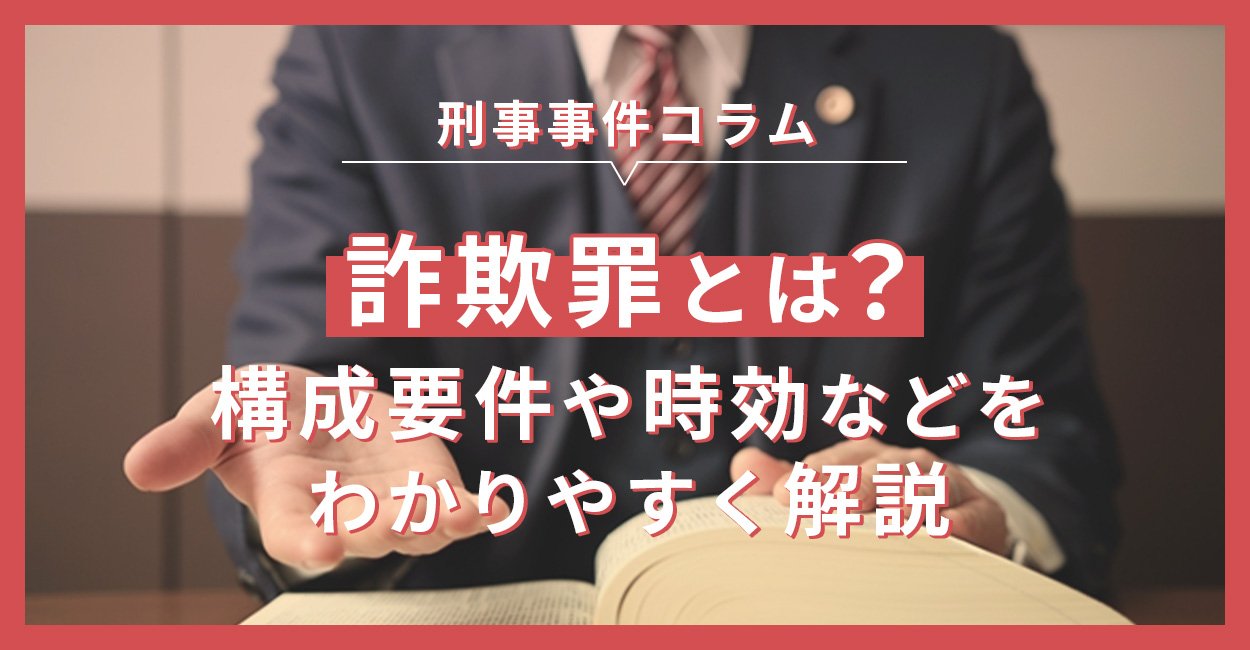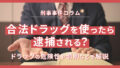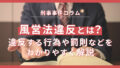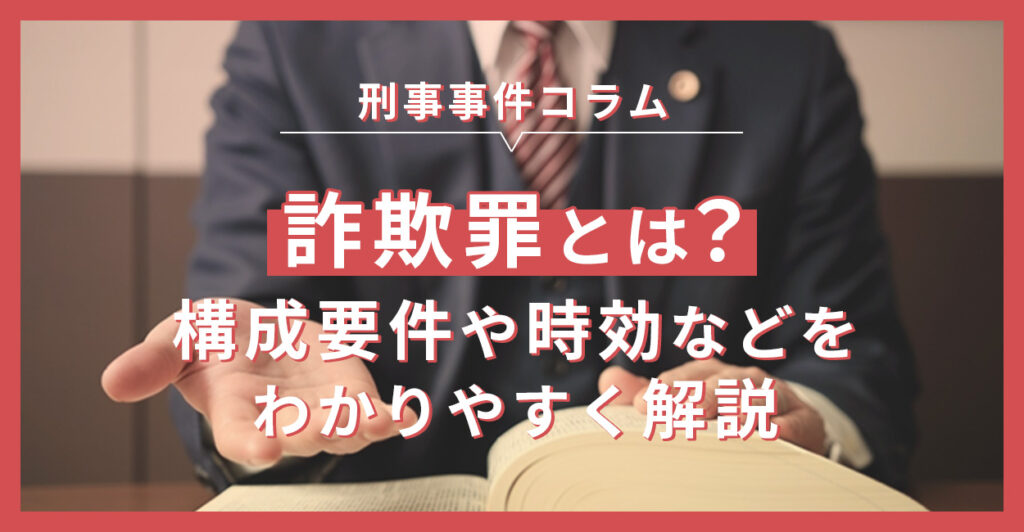
詐欺罪は、被害者から財物をだまし取る犯罪です。
近年は特殊詐欺による被害が大きな社会問題となっています。特殊詐欺に対しては重い処罰が科される傾向にあり、初犯でも実刑となるケースは珍しくありません。
今回は、詐欺罪について理解するため、詐欺罪の構成要件や時効、窃盗罪や横領罪との違いなどを解説します。
詐欺罪とは?
詐欺罪は人をだまして財物を交付させたときに成立する犯罪です(刑法246条1項)。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:e-Gov法令検索|刑法
詐欺の代表的な例としては、嘘をついて相手からお金をだまし取る行為が挙げられます。
近年、オレオレ詐欺や架空料金請求詐欺などの特殊詐欺が横行しており、2024年の特殊詐欺による被害額は約718億円にも上っています。
次の項目からは、詐欺罪について詳しく理解するため、詐欺罪の構成要件や時効、他の犯罪との違いなどについて解説します。
詐欺罪の構成要件
詐欺罪の構成要件は、次の4つです。
- 欺罔行為(人を欺く行為)
- 被害者の錯誤
- 被害者による財物の交付もしくは利益の移転行為
- 財物もしくは利益の移転
これら4つの構成要件の間に因果関係が認められると詐欺罪が成立します。
欺罔行為
欺罔行為(ぎもうこうい)とは、わかりやすく言うと人をだます行為のことを言います。
詐欺罪における欺罔行為は、財物の交付や利益の移転を目的としたものである必要があります。
嘘をついて相手をだましたとしても、それが財物を交付させる目的でなければ、詐欺罪は成立しません。
たとえば、「交通事故に遭って大けがをした」と嘘をついた場合でも、それが学校を休むためのものであれば、欺罔行為にはあたりません。
しかし、相手から入院費用をだまし取る目的のものなら、同じ嘘でも欺罔行為となるのです。
なお、自分自身で積極的に嘘をついていなくても、相手がだまされていることに気づきながら、あえてこれを伝えなかった場合には、欺罔行為と認定される可能性があります。
身近な例を挙げると、釣り銭が多いことにすぐ気付いたにもかかわらず、そのまま自分のものにしてしまった場合には、欺罔行為と認定される可能性があります。
被害者の錯誤
被害者の錯誤とは、被害者の認識と事実が一致しない状態のことです。
被害者が加害者の嘘を見抜き、錯誤に陥らなかった場合には、詐欺未遂にとどまる可能性があります。
詐欺罪が成立するには、それぞれの構成要件の間に因果関係が必要です。
被害者の錯誤があったとしても、それが欺罔行為によるものでなければ、詐欺罪は成立しません。
たとえば、商品を購入する際に、購入者の思い込みで形状や内容を勘違いしていたとしても、詐欺罪が成立しないのは当然のことです。
被害者による財物の交付もしくは利益の移転行為
詐欺罪の成立には、被害者の意思による財物の交付もしくは利益の移転行為が必要です。
つまり、錯誤に陥った状態での被害者の意思に基づく財産や利益の移転があるときに、詐欺罪の成否が問題となります。
加害者が被害者の意思に反して財物を奪い取った場合は、詐欺罪ではなく窃盗罪の成否が問題となります。
財物もしくは利益の移転
詐欺罪は、財物または利益の移転があった時点で既遂となります。
欺罔行為、被害者の錯誤、利益の移転行為があったとしても、利益の移転にまで至らなければ未遂罪が成立するにとどまります。
詐欺罪の時効
詐欺罪の罰則は、10年以下の拘禁刑です。長期15年未満の拘禁刑にあたる罪の公訴時効は、7年とされています(刑事訴訟法250条2項)。
なお、詐欺罪は、不法行為として民事上の損害賠償請求の対象となります。
詐欺行為に基づく損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知った時から3年、または詐欺行為時から20年です。
たとえば、詐欺行為から6年が経過したときに犯人が発覚したとします。この場合、公訴時効は成立していないので、刑事処罰の対象となります。
また、犯人が発覚したときから不法行為の時効が進むため、被害者が損害賠償を請求することも可能です。
詐欺罪と窃盗罪・横領罪との違い
詐欺罪は、同じ財産犯である窃盗罪や横領罪との区別が問題となるケースがあります。ここでは、窃盗罪と横領罪に分けて詐欺罪との違いを解説します。
窃盗罪との違い
窃盗罪は、被害者の意思に反して財物を奪い取る(窃取する)犯罪です。
財物の交付が被害者の意思に基づくのか、意思に反するのかによって詐欺罪と窃盗罪は区別されます。
また、詐欺罪は、だまし取る対象が財物だけでなく利益の場合にも成立します。一方、利益に対する窃盗罪は成立しません。
横領罪との違い
詐欺罪と横領罪は、財物の占有者が誰であったかによって区別されます。
詐欺罪は、被害者が占有していた財物をだまし取ったときに成立します。一方、横領罪は、もともと加害者が占有していた財物を自分のものにしたときに成立する犯罪です。
そのため、財物の占有がどのように移ったかが、両罪を区別する重要なポイントとなります。
詐欺によって占有が移った場合は詐欺罪、信頼関係などにより一時的に預かった財物を不正に処分した場合は横領罪が成立します。
まとめ
詐欺罪は、相手をだまして財産的利益を得る重大な犯罪であり、発覚した場合には厳しい処罰が科されます。
また、詐欺の被害に遭った側も、刑事事件としての対応とあわせて損害賠償請求などの民事的手続が必要になる場合があります。
詐欺事件は、事実関係の立証や法律上の判断が複雑になりやすいため、早い段階で弁護士に相談することが大切です。
状況に応じた適切な対応方法や今後の見通しについて、専門家の助言を受けることで最善の解決を目指せます。
詐欺事件でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。