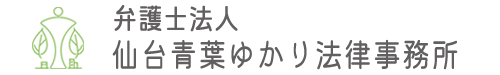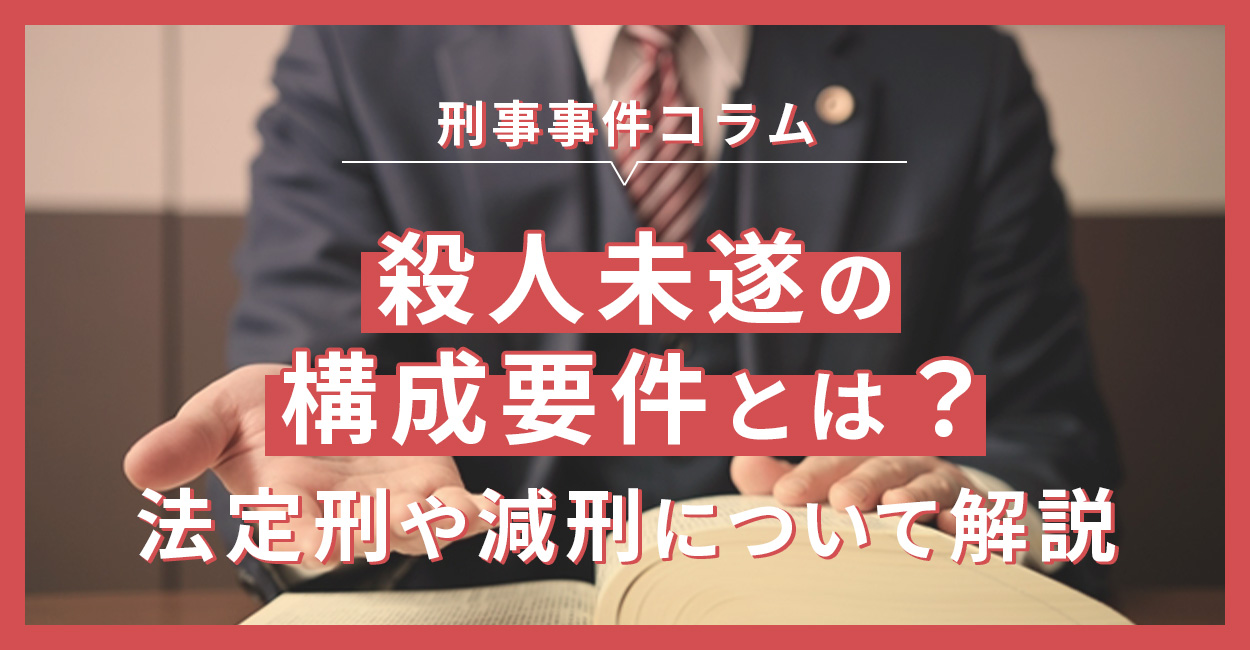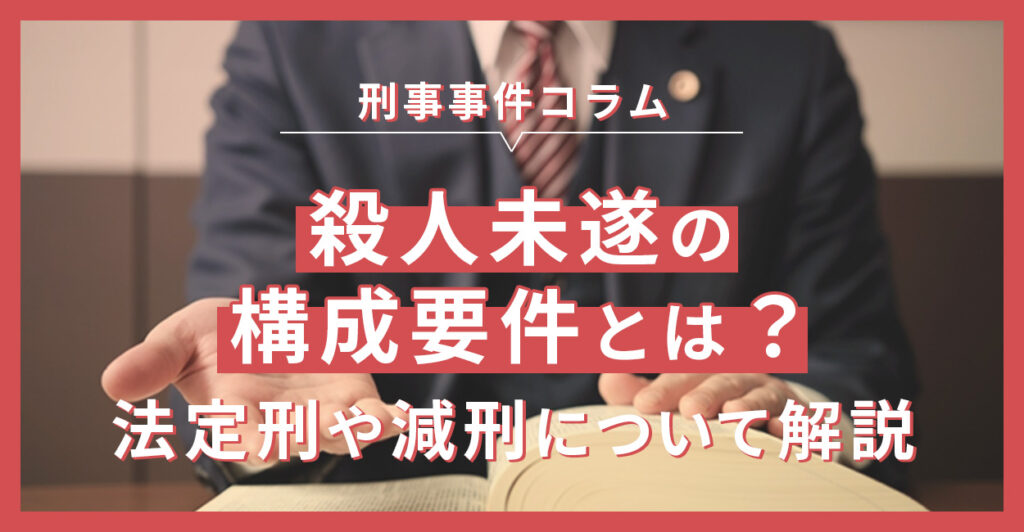
被害者を殺そうとしたのに、被害者が死亡しなかったときには殺人未遂罪が成立します。殺人未遂罪の法定刑は、死刑または無期、もしくは5年以上の有期懲役という重い刑罰が科される重大な犯罪です。
今回は、殺人未遂罪の構成要件、法定刑、減刑が認められるためのポイントについて解説します。
殺人未遂罪の構成要件
殺人未遂罪は、殺意をもって殺人の実行行為に及んだものの被害者が死亡しなかった場合に成立する犯罪です(刑法203条、199条)。
| (殺人)第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (未遂罪)第203条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 引用:刑法|e-Gov法令検索 |
殺人未遂罪の構成要件は、次の3つの要素から成り立っています。
- 殺意
- 殺人の実行行為
- 被害者が死亡しなかった
ここでは、殺人未遂罪がどのような場合に成立するのかを理解するために、構成要件の各要素について詳しく解説します。
殺意
殺意とは、相手を殺そうという意思のことです。殺意には、「相手を殺そう」という積極的な殺人の意思だけでなく、「相手を殺してもかまわない」という未必の故意も含まれます。
殺意の有無は、行為態様の客観的な危険性の有無によって認定されます。具体的な判断要素は、次のとおりです。
- 凶器の有無
- 凶器の形状・危険性
- 怪我の部位・程度
- 犯行後の行動
- 動機の有無 など
たとえば、出刃包丁で相手の腹部を刺した場合には、凶器や怪我の部位の危険性から殺意があるものと認定される可能性が高いでしょう。
殺意が認められない場合には、被害者が大きな怪我を負ったとしても殺人未遂罪ではなく傷害罪が成立します。
殺人の実行行為
殺人の実行行為と認定されるには、人が死亡する現実的な危険性のある行為であることが必要です。
たとえば、公園で被害者を突き飛ばす行為には被害者が死亡する危険性がないため殺人の実行行為とは認められません。しかし、囲いのないビルの屋上で被害者を突き飛ばす行為には被害者がビルから転落して死亡する現実的な危険性があるため殺人の実行行為と認定される可能性が高いでしょう。
被害者が死亡しなかった
殺人未遂罪が成立するのは被害者が死亡しなかったときです。殺意をもって殺人の実行行為を行いさえすれば、被害者が怪我をしなかったとしても殺人未遂罪が成立します。
たとえば、被害者に銃を発砲したものの手元がくるって当たらなかった場合、被害者に怪我がなくても殺人未遂罪が成立します。
殺人未遂罪の法定刑
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じ「死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役」です。刑法は、未遂犯と既遂の犯罪の法定刑に差を設けない代わりに、未遂犯については減刑の余地を認めています(刑法43条)。
| (未遂減免)第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 引用:刑法|e-Gov法令検索 |
未遂犯の減刑については、減刑することが「できる」と規定されていますが、殺人未遂罪については減刑を認めるケースがほとんどです。法律上は殺人未遂罪でも死刑や無期懲役の判決を下すことはできますが、実際に死刑や無期懲役となるケースはほとんどありません。
殺人未遂罪の量刑については、懲役3年から7年程度になるケースが多くなっています。未遂犯の減刑が認められた場合、有期懲役の下限が2年6か月(5年の2分の1)となるため、殺人未遂罪で執行猶予判決となる余地もあります。
殺人未遂罪の減刑が認められるためのポイント
殺人未遂罪で逮捕・勾留、起訴された場合に、減刑が認められるためのポイントは、次の3つです。
- 殺意がなかったことの証明
- 犯行に至る経緯・犯行態様についての情状
- 被害者との示談
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
殺意がなかったことの証明
殺意が否定されれば、殺人未遂罪は成立せずに傷害罪が成立します。傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」となっており(刑法204条)、殺人未遂罪の法定刑とは大きな差があります。
殺意を否定するには、単に「殺すつもりはなかった」と主張するだけでなく、客観的な状況から殺意がなかったことを証明しなければなりません。たとえば、犯行に計画性がなかったことや、犯行後に救命行動をとっていたことなどは殺意を否定する要素となり得ます。
殺人未遂罪ではなく傷害罪で処罰されるとなれば、減刑の程度は大きなものとなります。
犯行に至る経緯・犯行態様についての情状
犯行に至る経緯や犯行態様、犯行の動機などによっては、情状酌量による減刑が認められる余地があります。
たとえば、成人している子どもが父親に対する殺人未遂で処罰されるケースにおいて、幼少のころから父親が子どもを虐待していたことが動機であった場合には情状酌量による減刑が認められる可能性が高いでしょう。
被害者との示談
被害者との示談が成立している場合には、量刑が軽減される可能性が高いでしょう。
被害者の処罰感情は、判決の内容に大きな影響を与える要素の1つです。示談が成立し、被害者が被告人の処罰を求めていない場合は、量刑軽減の要素として判決で考慮されるでしょう。