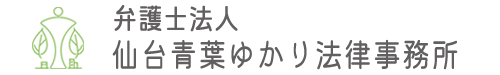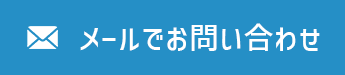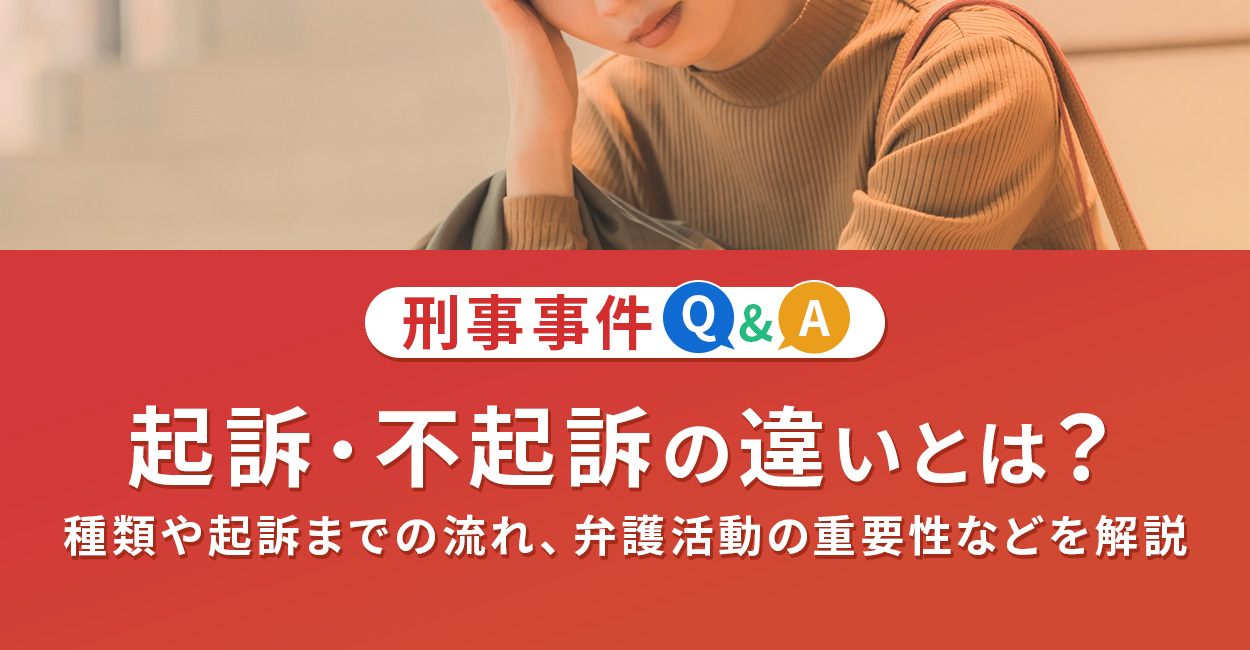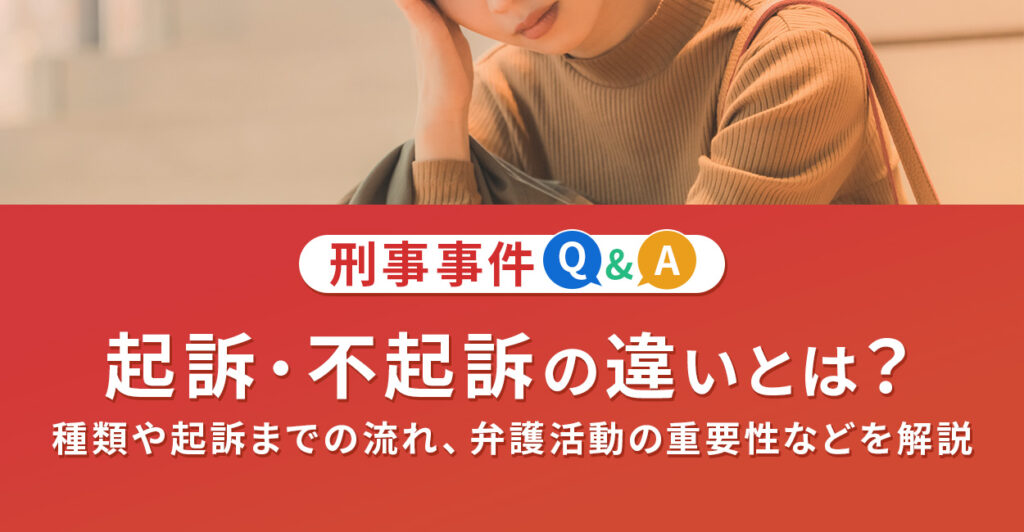

起訴されるとほぼ確実に前科がつくと聞いたことがあります。逮捕されたら必ず起訴されてしまうのでしょうか?

確かに、起訴されてしまうと前科がつくのを避けるのは難しいといえます。
しかし、逮捕されても不起訴で釈放されることもあります。
起訴とは、刑事裁判の開廷を求める手続きのことです。日本の刑事裁判では、有罪判決となる割合が非常に高いため、起訴されると前科がつくのは避けられません。
今回は、そもそも起訴・不起訴は何が違うのか、それぞれの種類や起訴までの流れ、弁護活動の重要性などを解説します。
起訴・不起訴とは
起訴とは、検察官が裁判所に対し、被疑者を裁判にかけて処罰を求める手続きのことです。これに対し、被疑者を裁判にかけずに刑事手続きを終えることを不起訴といいます。
起訴・不起訴を判断する権限は、検察官のみに認められています(起訴独占主義)。
日本の刑事裁判では、有罪率は99%以上と非常に高く、そのため、起訴されれば前科がつく可能性が極めて高いといえます。
前科がつくのは、懲役刑を受けたときだけではありません。罰金刑や執行猶予つき判決も前科になります。
起訴と不起訴には、それぞれ種類があります。
起訴の種類
起訴には、通常の手続きによる起訴と簡易な手続きによる起訴があります。
通常の起訴は、公開の法廷で刑事裁判が開かれ、被告人の処遇を決定するものです。
通常の起訴のことを「公判請求」といいます。検察官の提出する起訴状に基づいて裁判が進められ、検察官や弁護人が提出した証拠、証人尋問や被告人質問などの結果を踏まえて判決が下されます。
簡易な手続きによる起訴は、次の2種類です。
- 略式手続
- 即決裁判
略式手続は、被疑者の同意を条件として、書面審理のみで罰金または科料の判決が決定される手続きです。略式手続で懲役刑を下されることはありません。
略式手続は、交通違反の罰金事件で利用されることが多く、実務上は公判請求よりも略式手続の方が多く行われています。
即決裁判は、内容が明白で軽微な事案について、審理の開始から判決までを1日で終える手続きです。
即決裁判を利用できるのは、死刑、無期、または短期1年以上の懲役・禁錮に当たる重大事件ではなく、被疑者の同意がある場合に限られます。
また、即決裁判で懲役または禁錮刑が言い渡される場合には、必ず執行猶予付きの判決となります。
不起訴の種類
不起訴の種類(理由)には、主に次の3つがあります。
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
嫌疑なしは、捜査の結果、被疑者に犯罪の疑いがないと判断された場合の不起訴処分です。
嫌疑なしと判断されるのは、被疑者に明確なアリバイが判明した場合や真犯人が見つかった場合などです。
嫌疑不十分とは、捜査の結果、犯罪の疑いは残るものの、裁判で有罪の証明が困難であると判断された場合の不起訴処分です。
嫌疑不十分の場合、後に新たな証拠が発見されて再び捜査の対象となる可能性も否定できません。
起訴猶予とは、犯罪の立証が可能だが、情状を考慮して検察官の裁量により不起訴処分とすることを言います。
不起訴の理由の中で最も多いのは、起訴猶予によるものです。
犯罪の嫌疑が濃厚な場合でも、被疑者が十分に反省している、被害者との示談が成立している、被害弁償が行われているなどの情状が考慮されれば、不起訴処分となる可能性は十分にあります。
起訴・不起訴までの流れ
刑事事件の捜査は、被疑者の逮捕・勾留を経ずに進められるケースもあります。
この場合、事件が時効にかからない限り、起訴・不起訴の判断に期限はありません。つまり、在宅での捜査が長期間続いた後に、突然起訴されることもあります。
一方、被疑者が逮捕・勾留された場合、勾留の期間が満了するまでに起訴・不起訴の判断が下されます。
具体的には、逮捕から最長でも23日間で被疑者を起訴して裁判にかけるのか、不起訴として釈放するのかを決めなければならないのです。
被疑者として逮捕・勾留された場合でも、不起訴処分となれば前科はつきません。逆に、逮捕・勾留されていなくても、略式裁判で罰金刑を科されれば前科となります。
起訴前の弁護活動の重要性とは
これまでに説明したとおり、起訴されると有罪判決を受けて前科がついてしまいます。犯罪を犯してしまった場合でも、起訴猶予による不起訴処分を獲得できれば前科はつきません。
起訴猶予を得るためには、起訴前の弁護活動が重要となります。
起訴前の弁護活動の主な内容としては、次のものが挙げられます。
- 取り調べ対応についてのアドバイス
- 被害者との示談交渉
- 検察官との交渉・意見書の提出
取り調べで適切な対応をするには、弁護人からのアドバイスが重要です。
容疑を認めるべきか、黙秘すべきか、反省の態度をどのように示すかなど、専門家のアドバイスを受けることで適切な対応が可能となります。
被害者のいる事件で不起訴処分を目指すには、被害者との示談が何より重要です。被害者との示談交渉に弁護人は欠かせません。
刑事事件の経験・実績が豊富な弁護人が示談交渉を担当することで、示談成立の可能性が高まり、適切な金額での示談が可能となります。
起訴・不起訴の判断を下すのは検察官です。起訴猶予を獲得するには、被疑者が十分に反省していること、被害者との示談が成立していること、被害弁償を行っていることなど、有利な情状を検察官に伝える必要があります。
弁護人は、検察官との交渉や意見書の提出を通して、起訴猶予の判断に必要な資料や事情を検察官に伝えます。
まとめ
起訴・不起訴の判断は、被疑者の今後の人生に大きな影響を及ぼします。しかし、適切な弁護活動によって、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
刑事事件においては、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、最良の結果につながる第一歩です。
取り調べへの対応や示談交渉、検察官との交渉など、専門的なサポートが必要な場面では、経験豊富な弁護士の力が不可欠です。
起訴・不起訴の判断や今後の対応について不安を感じている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。